キーボード
キーと呼ばれるボタンを押すことで、対応する文字や数字を入力する。ファンクションキーやエンターキーなどでプログラムの実行を指示できる。英語キーボード(101)、日本語キーボード(106,109)など、種類によって若干キーの配列が変わる(変換ボタンなど)。

動作周波数(内部クロック・クロック周波数)とは、各回路で処理を行うタイミングを取る周波数で、動作のスピードを表す。単位は「Hz」である。また、CPUとチップセットのデータの受け渡しに使う信号の周波数はFSB(フロントサイドバス)と言う。こちらも高ければ、動作が速くなる。
CPUの「コア」という実際の処理部分がある。現在は複数のコアを搭載しているCPUが主流。ただ、コアが2つや4つに増えたからと言って、2倍、4倍にはならない。
レジスタはCPUが処理する指示やデータの場所を格納する記憶装置である。レジスタの情報がCPUの回路に送られて処理を行う。
また、CPUはすぐ熱くなるので、冷却グリスや冷却ファンは必須である。ファンが止まると直ぐに壊れることもある。
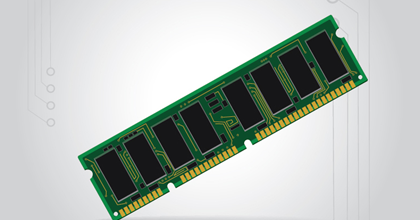
ROMにはBIOS(Basic Input Output System)という、コンピューターが一番最初に実行されるプログラムが書き込まれている。周辺機器を制御したり、自己診断を行った後、OSに引き継ぐ。BIOSが記憶している情報をCMOSと呼ぶ。
外部に装着されることも多い。電源を切ってもデータは残る。
ハードディスク:必須のハードウェア。磁気ディスクを使用し、高速回転させることで磁気ヘッドがデータの読み書きを行う。
CD-ROM,DVD-ROM:光学メディア。読み出し専用だが、CD-R,DVD-Rなどは書き込みもできる。
フラッシュメモリ:構造が単純で、安価で大容量の保存が出来る。
SSD:solid state driveの略。呼び出しが速く、データの保存も出来る。書き込みは特別速い訳ではないが、コンピューターの高速化に貢献している。
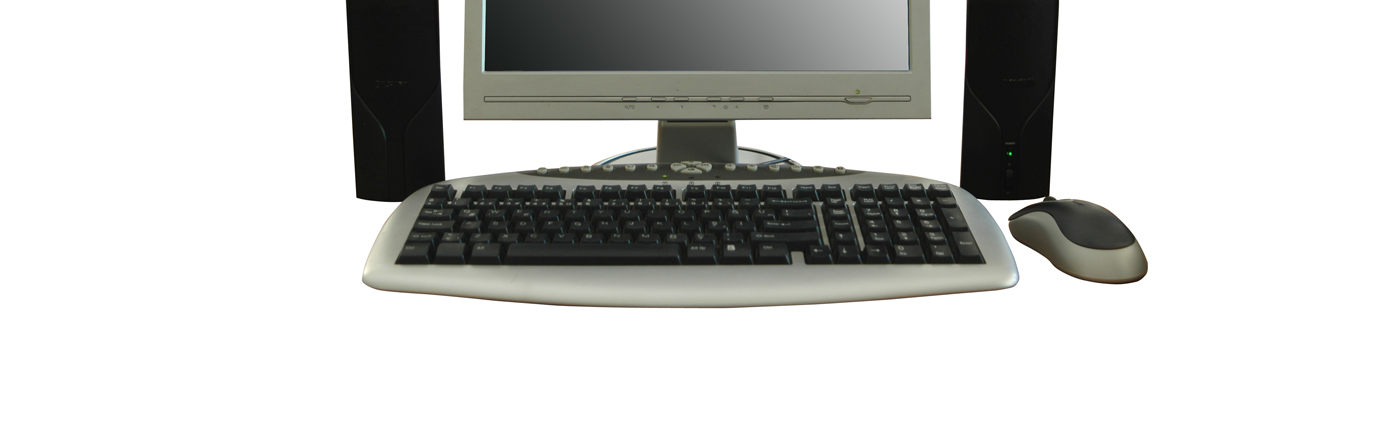
コンピューターに指示や情報を与える。様々な装置がある。
キーと呼ばれるボタンを押すことで、対応する文字や数字を入力する。ファンクションキーやエンターキーなどでプログラムの実行を指示できる。英語キーボード(101)、日本語キーボード(106,109)など、種類によって若干キーの配列が変わる(変換ボタンなど)。
ポインティングデバイスの代表。マウスの動きに合わせて画面上のポインタが対応して動く。GUIがOSで採用されてから、直感的に操作できるインタフェースとして必須なものである。
トラックパッドはノートパソコンなどについており、指で揺れると動きを探知し、画面上のポインタが動く。タッチパネルはディスプレイに設置されており、直接的にGUIを操作できる。
デジタルカメラは景色をデジタル化し、補助記憶装置などに記憶する装置。スキャナは紙に書かれた図形や写真を読み取って、デジタル化し取り込む装置。
Natural User Interface。人間の動きをデジタル化し取り込む。Kinectやリ―プモーションなど。

処理結果をユーザーに伝える。
文字や画像を見せる装置。CRTディスプレイ(ブラウン管)、液晶ディスプレイなどがある。
データを紙に印刷する装置。インクジェットプリンタやレーザープリンタなどがある。
音を聴かせる装置。スピーカーや人間の耳に装着するイヤフォンなどがある。
東京都内からも近い千葉県の船橋駅近くで文系向けプログラミングスクール(個別指導)を開講しています。未経験WEB担当者の育成にもお役立てください。
お気軽にお問い合わせください。
千葉県のsomosomoプログラミングスクール